年初だけは勢いよく上げたものの米国はNASDAQを中心に大幅下落の1月となっています。
日経平均も下落だけは日米同盟でキッチリお付き合いするのですが、米国株がグイグイ上昇している時は横ばい推移なのに面白い株価指数ですね!?(下方向の強さだけはNASDAQ級!)
NASDAQ総合は昨年11月の最高値から15%超の下落、年初からは12%近い下落となりダウやS&P500も大きく下落しています。
米国がこれだけ下がるとリスク回避から世界中の株価がお付き合いして下げるのが常ですが、今回はそうなっていないことが特徴的かも知れません。
新興国の香港・インド・ブラジル等はまだ年初来でプラス圏を維持しています!
1カ月チャートを見ると年末年始の動きは少ないので年初来騰落率に近い結果になると思いますが、チャート目視なので±1%程度の誤差はあると思ってください。
1カ月騰落率は、香港+7%、ブラジル+4%、インド+2%、上海▲3%となっています。
上海だけが米国の動きに反して浮上するのはよくあるのですが、自由化されている香港でこれだけ上がっているということは世界の投資家の総意であり、米国の下落とここまで反比例するのは珍しいと思います。
香港ハンセン指数は香港市場というより香港上場中国本土銘柄の影響が大きい指数です。
まあ米国が利上げサイクルに入る一方で中国は景気刺激で利下げするという動きもありますからね。
米国がかなり割高の水準で新興国がかなり割安の水準からの米国株崩れなので新興国が影響を受けにくいという面は確かに大きいと思います。
でもインドは昨年米国同様に株価好調だったのに値崩れしていないし、なんと言っても横ばい日経平均がメタメタに売られている説明がつかない!?
(日経は日経で世界の中でもかなり特異特殊な指数なので例外扱いでは・・?)
香港の上昇率が一番高いのは昨年マイナス圏に沈んだ反動という面が大きいのは否めません。(じゃあ日本は?)
新興国と言っても、台湾韓国のようにコロナショック後のハイテク買いで恩恵を受けた国もあれば、かなりアレなエルドアン率いるトルコも含まれる訳で一括りにして語るのは大雑把過ぎるのですけどね。
個人的には新興国投信やETFというミ〇もク〇も一緒にしたパッケージではなく国別に細分化して低コストで投資できる環境を望みます。
単純に大国米国vs新興中国(古豪復活)という枠組みや覇権争いの中で新興国の多くが中国側の陣営に加わっている訳でもありません。
米国株が軟調でも中国が堅調を保てば影響を免れデカップリングで中国株が上昇して世界の株価を今後引っ張るという序章を2022年初の株価動向が表現している訳でもないかも知れません。
一般的には米国利上げが新興国からの資金流出と景気を冷やす対抗利上げを招き、2022年は米国のみならず新興国も巻き込んで厳しい年になるという予測ができます。
しかしながら、2021年までに買われ過ぎて割高な米国株と割安に放置されて来た(大雑把な括りですが)新興国という構図の中で、1月のように米国の下落圧力に抗い上昇する力強さを2022年通して新興国が見せてくれることを期待します!
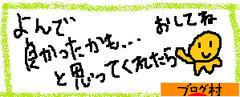 にほんブログ村
にほんブログ村
2022年は新興国の逆襲なるか?米国は年初から大幅下落も新興国はプラス圏を維持!
 新興国
新興国