今週26日にインド株連動ETF(1678)が東証に上場されます。
このETFの正式名称は「NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信」ですが、その名の通りS&P CNX Nifty指数との連動を目指します。
しかし、この指数は一体何なのでしょうか?
私も通常インド株の指数はBSE SENSEX指数をチェックしますし、メディアでインド株が何%上がった下がったと言うのも通常BSE指数を元にしています。
S&P CNX Nifty指数は、1994年設立のナショナル証券取引所(NSE)で取引される24業種の代表50銘柄で構成される時価総額加重平均の指数です。
これで、同取引所の時価総額の65%(09年3月末時点)を占めています。
一方、BSE SENSEX指数は、1875年設立でアジア最古のムンバイ取引所(BSE)で取引される代表30銘柄で構成される時価総額加重平均の指数です。
インドで時価総額が一番大きい証取はムンバイなので、日本で言えばムンバイが東証でナショナルが大証のようなイメージを持つかも知れません。
じゃあ、Nifty指数は大証の平均指数みたいなもんか?
なんでBSE指数じゃないんだ!大丈夫なのかと心配になりますね!?
しかし、重複している銘柄も多くインドの株価平均を買うという意味では大きな差はないと言えます。
下はBSE指数とNifty指数(^NSEI)の過去5年のパフォーマンスを比べたものですが、長期では差が生じていないことがわかります。
(差が開くときは常にBSEが上回っているようですが!?)

では何故Nifty指数に連動させたかというと、たぶん東証がナショナル取引所と提携しているからという理由だけでしょう・・。
海外ETFなら2つの指数に連動するETFを選べますが、日本ではノーチョイスですし、BSE連動じゃないから買わないと言う人はかなりのマニアでしょう。
インド株価の平均を買うという意味では、Nifty指数連動でも充分だと思います。
因みに、HSBCインドオープン等の投資信託がベンチマークしているのはS&P/IFC Investable India(円ベース)というこれまた異なる指数です。
外国人の売買が制限されていて銘柄選択に支障があるので、海外投資家のために別の指数が用意されています。
そういう意味でも、インド国内の株価指数に連動するETFに投信から資金を移せばコストも下がって分散にもなると思います。
ということで、Nifty指数連動であることはあまり気にする必要はないと思いますが、BSE SENSEX指数とは構成銘柄が異なるので、当然のことながらパフォーマンスに若干違いが生じることは頭に入れておいた方が良いと思います。
では次に、国内ETF新規上場=天井サイン説がまだ生きているのかを検証してみましょう!?
数々の天井をピタリと当ててきた国内新規上場ETFですが、最近は数も増えて、その傾向も薄れてきたかも知れません。
私が心配した8月に登場したWTI原油価格連動ETF(1671)も暴落はしませんでしたが、・・・ほらやっぱり上場直後が高値で飛びついた人は儲かってないじゃない!(↓)
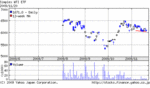
インド株もタイミング的にはこの辺で頭を打って揉み合いか下げモードに入っても全然おかしくはないと思います。
今回はブラジル・ロシアの上場から1年半遅れですし流行を追ったのではないと思いますが、なんせ過去の逆指標っぷり、いや天才的な天井的中率を私は軽視することが出来ないのです!?
何れにしても上場直後は過熱気味で指数から上方乖離する可能性が高く、買うなら基準価額をしっかり確認して高値掴みは避けた方が良いと思います。
(これはインド株価指数自体が高いか否かとは別問題です。)
後日、私なりの新興国ETFの買い方と使い方を書いてみるつもりです。
![]() [←参考になりましたら一押し。m(._.)m]
[←参考になりましたら一押し。m(._.)m]


コメント
インドはファンドの対象指数がよく分かりませんよね。
私のメインの投資先のLyxor Indiaや野村インド株ファンドはMSCI India Indexがベンチマークで、HSBCインドはS&P/IFC Investable India
だったり^^;
どの指数が運用の世界では最も参考にされているのでしょう・・・なんて気になってしまいます。
そうですね、インド国内で重複上場というのもよくわかりません。
インドは指数のわかりにくさもありますがコストも若干高めなので、外国からの投資制限が緩和されていけば投資コストも下がると思うのですけど・・。
BRICsの中でも外国の個人が個別銘柄に投資できないのはインドだけだと思います。
(日本からは実質ブラジルも出来ませんけど)